
|
電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト
© Copyright IEICE. All rights reserved.
|

|
電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト
© Copyright IEICE. All rights reserved.
|
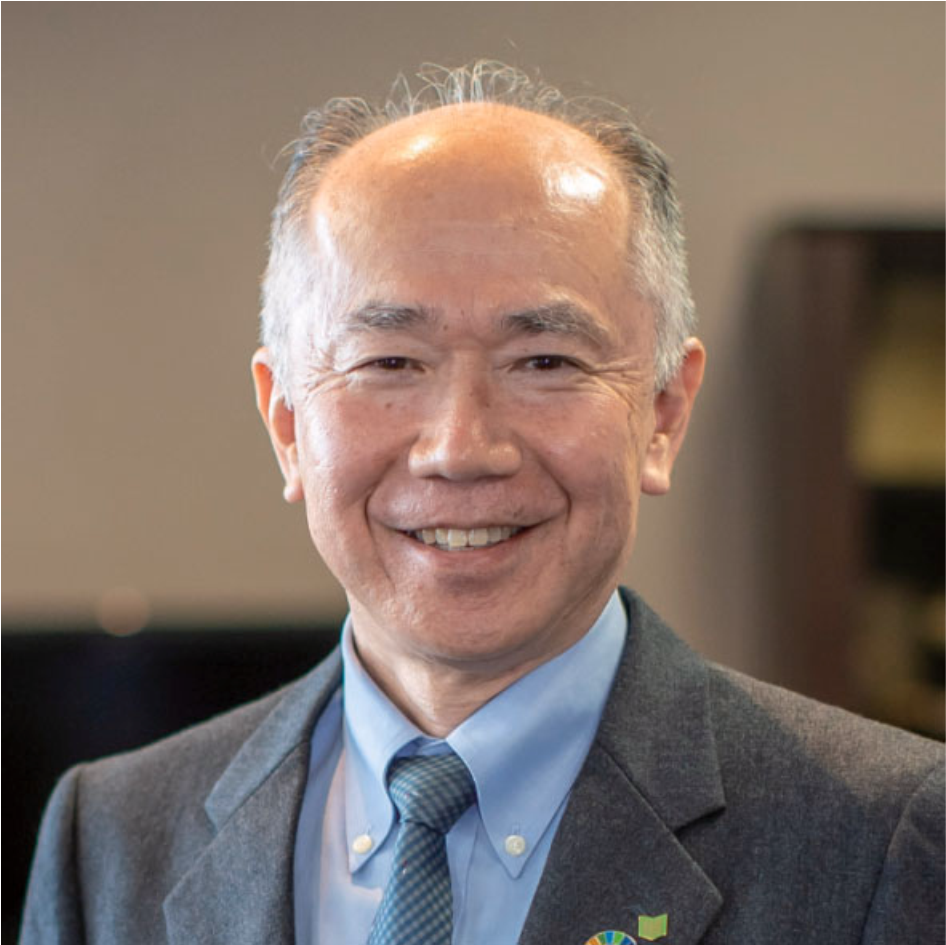 |
東海地方は,古くから我が国の産業・文化の要として発展してきましたが,一方で南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害のリスクと隣り合わせにあります.伊勢湾を囲む愛知,岐阜,三重,更に静岡西部を含む地域は,豊かな自然環境と強じんな産業基盤を持つ反面,地震・津波・台風などの自然災害に繰り返し見舞われてきました.この地で暮らし産業や学術活動を営む者にとって,「防災・減災」は日常の延長にある重要課題の一つで,その取組みを支える中核となるのが,近年目覚ましい進化を遂げている情報通信技術です.
情報通信技術は,従来の情報伝送のみならず,IoT,AI,ビッグデータ解析やクラウドコンピューティングなど多様な技術との融合へと発展しています.これらの技術は,防災・減災の現場でも広範に活用されており,例えば,沿岸部や河川に設置された高感度センサとカメラからの情報を集約してAIが解析することで,災害兆候をリアルタイムに把握できます.異常検知と同時に警報を自動発信して避難の迅速化を図るシステムは,既に実装が進んでいます.
こうした技術活用の重要性は,先の能登半島地震でも浮き彫りになりました.大規模停電や道路寸断が発生する中,可搬形衛星通信設備が被災地に展開され自治体や救援機関間の情報共有を支え,ドローンによる撮影映像は孤立集落の状況把握や物資輸送ルートの選定に活用されたようです.また,SNSなどでの住民発信情報は,公式の被害報告を補完し,避難所運営や安否確認に貢献したと聞きます.これらは,災害直後における通信確保の重要性と,平時からの多様な通信手段とその運用を訓練しておく備えの重要性を私たちに強く教えてくれます.
南海トラフ巨大地震は,能登半島地震を上回る広域かつ同時多発的な甚大な被害をもたらすと予測されています.道路や通信,電力などのインフラが寸断される中で被災状況を的確に把握し救援活動を行うためには,冗長性と耐災害性を備えた情報通信インフラが不可欠です.非地上系ネットワークNTNや被災直後から稼動可能な可搬形基地局,災害時優先通信システムなどの研究開発は,その象徴的な取組みです.また,復旧・復興期においても,避難所管理や物流トラッキング,被災者支援情報の一元化などにおいて,情報通信技術が果たす役割は計り知れません.
一方で,こうした技術やシステムを有用に機能させるには,人材と連携が必要です.三重県と三重大学は,地域の防災リーダを育成する「みえ防災塾」を開講しており,行政職員,企業,防災団体,学生が共に学び,実践的な訓練を行っています.ここでは,情報通信技術の活用や災害時の情報共有方法も重視され,異なる立場の参加者が顔の見える関係を築くことで,災害対応力の底上げが図られています.こうした取組みは,技術と人を結び付ける地域防災の好事例と言えるでしょう.
情報通信分野に携わる私たちは,災害に強い社会を構築するための知見と技術を提供する責務を負っています.本会は,そのための知識共有と議論の場であり,最新の研究成果や事例紹介を通じて,新たな発想や協働の機会を提供することを目的としています.東海地方をはじめとする全国が抱える災害リスクを直視し,そこから導き出される課題解決に情報通信技術を最大限活用することは,地域や我が国における安全・安心の向上だけでなく,世界の防災・減災モデルの創出にもつながります.会員の皆様の知見と経験が集まり,新たな「防災・減災」への取組みが本会から発信されることを,心から期待しています.
オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。
電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。
電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード