
|
電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト
© Copyright IEICE. All rights reserved.
|

|
電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト
© Copyright IEICE. All rights reserved.
|
解説
ICTによる新社会システム創成と生産性[Ⅰ]
――ICT研究開発とシステム創成論の導入部――
Innovating Social Systems via ICT, and Productivity[Ⅰ]: R&D of ICT and Introduction to Systems Innovation Theory
A bstract
本稿はICTによる新社会システム創成と生産性を2回構成で論じる第1回に当たり,情報通信技術(ICT)による新社会システムの創成に関係する幾つかの言葉とシステム創成論の導入部について述べている.本稿の前半では,初出から場合によってやや概念が変わりながらも広く使われている幾つかの重要な言葉について述べ,後半ではシステム創成論の導入部として,進化の三段階,ICTの本質,システム創成の位置付け,社会に定着しやすいシステム創成の三要素などを,具体例としてP2PシェアリングビジネスやAmazonを取り上げながら説明している.
キーワード:研究開発施策課題設定,メタ議論,シェアリングビジネス,社会変革
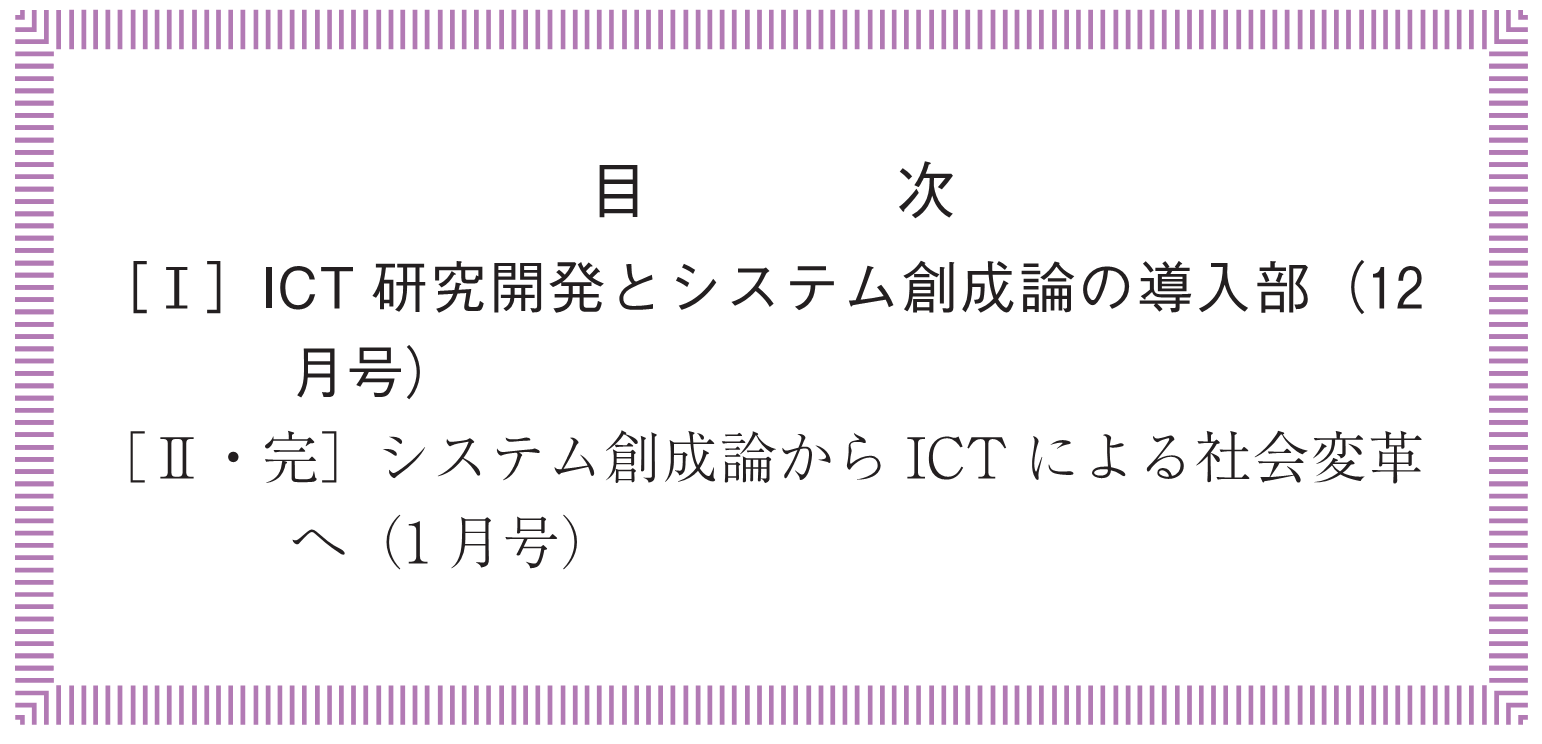
本稿は,分野を超えた研究開発施策課題創成に関するメタ議論であり,誌面の都合で2回に分けて述べさせて頂く.その第1回である本稿では,テーマに関連する幾つかの言葉に触れた後,システム創成論(1)~(18)の導入部に関して述べる.第2回では,プラットホーム論を含むシステム創成論を紹介した後,生産性に関する思考実験的議論を試みる.
筆者は週休6.5日制を遠望して,それに近付ける新社会システム創成の実現可能な道程を模索している.電子情報通信学会の各会員が日々研究開発に取り組む情報通信技術(ICT: Information Communication Technology)は単なる情報通信インフラを支える技術であることを超えて,事業構造そのものを変えるような様々な社会変革,ライフスタイルの変革を起こしてきた.これまで学会や産学官連携の場でシステム創成論に関係するお話をさせて頂く中で筆者は,ICTによる新社会システムが社会を変革する大きな影響を与えてきたことを述べてきた.
システム創成論に関するテーマは,基本となる普遍性の高い考え方に基づきながら,新たなシステムの創成は起こり続けるため,特に具体部分に関しては執筆や講演時点までの記述とならざるを得ない.本稿は,編集委員会から執筆依頼を頂いた機会に,2024年上半期までの筆者の考えをまとめた記事であることを御承知おき頂きたい.また,様々な根っこからこの種のMeta理論が生まれて,似ている部分も異なる部分もあるが,本稿では筆者が2000年以降進めてきた内容を中心に述べる.エッセイのようにお読み頂ければ幸甚である.
1980年代の終わりにはMark Weiserによる“Ubiquitous Computing(19)”の提唱,1992年にはNeal Stephensonの小説に初出となる“Metaverse”(20),1999年にはKevin Ashtonによる“Internet of Things(IoT)”(21),2002年のMichael Grievesによる“Digital Twin”(22),2004年にはErik Stoltermanによる“Digital Transformation(DX)”(23)といったように,1989年頃からの15年間は,現在でも研究開発やビジネスの世界で様々な議論が交わされる重要な言葉や概念が次々と生まれ,あるいは提唱されてきた.
続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。
電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。
電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード